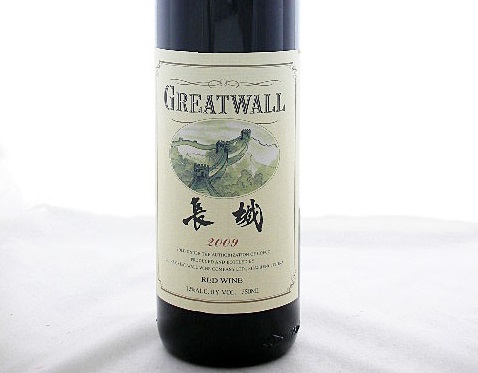「♪黄砂に吹かれて~きこえる歌は~」。これは、工藤静香の往年の名曲「黄砂に吹かれて」の冒頭の一節だ。広大なシルクロードの旅を連想させるようなロマンあふれる歌詞といえる。しかし、実際の黄砂はそんなロマンチックなものではなく、砂塵が日照を遮り田畑を覆い尽くすなど農業に甚大な被害をもたらす。
日本にもこの春、各地に黄砂が飛来した。ただ、被害は洗濯物やクルマが汚れるといった程度で、農作物へ影響が出るほどのものではない。何といっても発生源である中国の黄河流域である。古代文明の時代から否応なく黄砂と付き合わざるを得ず、それに適した農作物のみしか栽培することが出来なかった。米ではなく、小麦、粟(アワ)、果樹類などである。
近年、この黄河流域が世界の注目を集めている。ワイン用ブドウの栽培である。乾燥した気候、少ない降水量、砂のような土壌・・・。稲作には全く向かないこの環境がブドウ栽培には持ってこいなのである。中国のワイン生産量は2000年頃から急速に増え続け、現在世界で第7位(ちなみに日本は26位)。堂々たるワイン大国と言っていい規模であり、今後もっとも成長が期待されている存在なのだ。
とは言っても、中国ワインを飲んだことはおろか、見たことも聞いたこともないと言う人がほとんどではないだろうか。そりゃ、そーだ。どこのワインショップを見渡しても中国ワインなんて置いてやしないし、ホテルの本格中国料理店でもワインはあってもフランス、イタリア、カリフォルニア、チリなど、その名を知られた産地国のものばかりである。
じつは筆者は、もう10年以上前ではあるが、中国ワインを飲んだことがある。札幌の中華料理店で何かの宴会の席だったと記憶している。常時メニューにあるという訳ではなく、販促キャンペーンでの特別出品だったと思われる。「長城」という名の赤ワインだった。中国でワインを造っていることを初めて知った。恐る恐るボトル一本を注文した。ラベルには万里の長城の絵が描かれていた。
で、お味は?ということだが、抜群に旨いということはなかったが、けっして不味くはなかった。品種はカベルネ・ソーヴィニヨン主体で、海外のデイリーワインクラスのクオリティはあった。現在、黄河流域にはボルドーを代表するワインメーカーであるシャトー・ラフィット・ロートシルトを筆頭に海外の大手メーカーが数多く進出。現地での技術指導やワイナリーを直営するなど、世界市場で通用する高品質ワインが続々と生まれてきているという。
中国の国内でのワイン消費量は、米国、フランス、イタリア、ドイツに次いで世界第5位。6位のイギリスを大きく引き離す勢いだ(ちなみに日本は15位)。ただし、内訳は輸入ワインがほとんで、北京、上海、広州など、大都市の富裕層が購入しているに過ぎない。また、粗悪な偽造輸入ワインも大量に出回っており、信頼できる国産ワインの普及拡大が望まれている状況だ。
課題も多いが、将来性もまた限りなく大きい昨今の中国ワイン市場であった。さて、黄砂で汚れたクルマをすっきりと洗い終えたあとは、はるか黄砂の国に思いを馳せながら、回鍋肉か麻婆豆腐あたりでもペアリングのお供に、久々にこの長城ワインで一杯飲るとしましょうか。
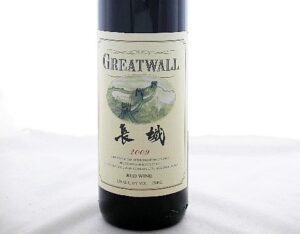
長城 (GREAT WALL)
生産地:中国河北省沙城地区
生産者:長城葡萄酒有限公司 品 種:カベルネ・ソーヴィニョン主体 価格帯:1300円(税抜)~