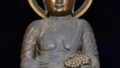“樽生”と聞いて、何を連想するだろうか?普通はやはり、樽生ビールだろう。アサヒやキリン、サッポロ、サントリーなど大手各社では、飲食店で飲める本格生ビールとして、この樽生ビールの一層の品質向上に力を入れ続けている。じつは、ワインの世界にも「樽生ワイン」というものがあるのをご存じだろうか。
 シャトレーゼの「樽出し生ワイン」
シャトレーゼの「樽出し生ワイン」
ワインの本場であるフランスやイタリアでは、酒屋の店先にワイン樽が置かれており、量り売りで普通に売られている。日本で見かけることはまずないが、ある日偶然、スーパーのお菓子売場で「樽出し生ワイン」というものを見かけたのだ。それは、全国640店舗を展開する洋菓子チェーン「シャトレーゼ」のテナントだった。そこでは何と!樽生ワインの量り売りをやっていたのだ。
お菓子の会社が、なぜワインを?と疑問に思うかも知れないが、シャトレーゼは山梨県甲府市に本社を置く山梨発祥の企業であり、創業者はもともと山梨県勝沼町のブドウ農家の長男なのだ。そもそも「シャトレーゼ(Chateraise)」という社名からして、フランス語の【château】(シャトー)=「城」と【raisins】(レザン)=「ブドウ」を組み合わせた造語であり、ワインに対する並々ならぬ想いが込められているものだったのだ。
洋菓子事業の全国展開が軌道に乗った2000年(平成12年)、創業の地であるブドウ王国・山梨の原点を見つめ直し、新規事業として勝沼町にワイナリーを開設したのだという。樽出し生ワインは、シャトレーゼのほとんどの店舗で取り扱っている。赤は「カベルネ・ソーヴィニヨン」と「メルロ」、白は「シャルドネ」の計3種類で、それぞれ836円(税込)。量り売りには初回のみ、専用のリユース瓶203円(税込)を購入する必要があるが、それでも1039円(税込)という安さだ。
通常、日本国内で栽培したこの3品種のブドウを使ったワインを、この価格で販売するのは生産コストから考えて不可能である。3000円~4000円に設定するのが普通だ。表示を注意深く見てみると、やはり「輸入ワイン使用」とあった。店頭にはなかったが、「甲州」種を使用した白ワインも同価格で販売しており、こちらは山梨県産の甲州のみを使用した正真正銘の日本ワインとなる。ただし、山梨のワイナリーでのみの限定販売となるそうだ。
また、パンフレットには「無濾過・非加熱の生ワイン」とあった。近年、「ナチュール」(ナチュラルワイン)、つまり“自然派ワイン”というものが人気を集めているが、こちらもそれを意識したものと思われる。じつは、ナチュールには厳密な規定がない。一応「有機栽培などで出来るだけ無農薬でブドウを育て、化学的な添加物と人為的介入を極力減らして醸造されたワイン」といった程度である。
ちなみに「オーガニックワイン」には、他の農作物と同様に有機栽培に関する厳密な規定があり、これに則って認証を受けたブドウを使用したワインのみが名乗ることが出来る、ただし、醸造については規定外である。ナチュールは、栽培と醸造の両方の過程に配慮しているという意味で、“より自然派”というイメージに受け止められているのだ。“生ワイン”についても、規定はないが似たような印象を与えると言えよう。
“無濾過”というのも、ナチュール全般で強くアピールしているポイントだ。フィルターで濾過するのは、ブドウの皮や梗、発酵済の酵母カスなどの不要物を取り除く、醸造における重要なプロセスだ。ナチュールでは、これを“人為的介入”と考えるため、まったくのノンフィルター、もしくはごく軽いフィルターのみを用いることで、ブドウ本来の風味成分を出来る限り生かそうとする。ただし、よほど慎重に行わないと雑菌が繁殖し、ワインそのものを台無しにしてしまうというリスクもはらんでいる。
さらに、“非加熱”とある。「え、ワインて加熱してるの?」と驚く方も多いと思うが、19世紀の中頃まで、ワイン造りにおける最大の課題は“いかにしてワインの腐敗を防ぐか”ということだったのだ。この難題を解決したのが“近代細菌学の父”と呼ばれるフランスの微生物学者ルイ・パスツールだ。1866年、彼はアルコール発酵が酵母菌の働きによることを発見し、さらに腐敗の原因が有害な雑菌の仕業であることを突き止める。そして開発したのが、「低温殺菌法」という方法だ。
“低温”というとマイナスの温度を連想するが、この場合は100℃以上の高温に対しての低温であり、ワインの場合55℃~60℃の温度で一定時間加熱することを意味する。これにより、微生物を完全に死滅させることなく、害のない程度にまで減少させ、素材の風味を損なうことなく腐敗を防止することが出来るのだ。同様の方法は、“生ビール”ではないビール、すなわちキリンラガービールやサッポロ赤星などの「熱処理ビール」にも使われている。
ただし、ワインに関して言えば、低温殺菌法は現在ほとんど使われていない。それは工場の衛生管理体制や濾過技術の飛躍的な進歩によるものだ。念のため、<vol.9>にも登場した高畠ワイナリー製造部門のI田さんにも確認してみたところ、高畠ワイナリーでも加熱処理は一切行っていないということだった。その代わり、濾過に関してはブドウ果汁の種類ごとに濾過器とフィルターを使い分け、何段階かに分けて慎重に行い、ワインに負荷がかからぬよう細心の注意を払っているということだ。そのような現状が一般的であるだけに、ことさら“非加熱”を強調する必要はないのではと思われるのだが。
 ドラフトワイン・システムの料飲店用「樽生ワイン」
ドラフトワイン・システムの料飲店用「樽生ワイン」
もうひとつ注目されている、樽生ワインがある。神戸市に本社を置く「ドラフトワイン・システム」では、フランスやイタリアの現地ワイナリーで、ワインを特殊なステンレスタンクに直接樽詰めして輸入している。タンクには窒素が充填される仕組みなので、ワインが空気に触れることなく酸化を防ぎ、現地での飲み頃の味を一定期間保つことが出来る。主に料飲店向けのハウスワインとして「樽生ワイン」の名で提供している。画期的なシステムではあるが、現在のところ関西エリアが中心で、北海道での採用実績がまだ数店しかないのが惜しまれる。
 業務用3リットルのBOXワイン
業務用3リットルのBOXワイン
樽生ではないが“箱生”と呼ばれる、主に業務用で使われている3リットルのBOXワインというものもある。紙パックの箱の中には真空パックされたワイン袋が入っており、注ぐたびに袋が萎んでいく仕組みなので、ワインを空気に触れさせず酸化を防ぐ効果がある。ワインの品質を保つ工夫はさまざまであり、新しい手法が次々と開発されている。まずは手軽なところで、シャトレーゼの量り売りから試してみるのはいかがだろうか。

シャトレーゼ樽出し生ワイン
生産地:山梨県甲斐市
生産者:シャトレーゼ ベルフォーレワイナリー
品 種:メルロ
価格帯:836円(税込)+リユース瓶203円(税込)