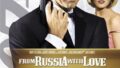「ピラフ」というものを、もう何年も食べていない。かつてピラフは、スパゲティやカレーライスと並び、喫茶店の軽食メニューの定番だった。他の2つがその後、多くの専門店を誕生させ本格料理へと進化したのに比べ、ピラフの専門店というのは聞いたことがない。そもそもピラフとは、どこで生まれどのようなルーツを持つ料理なのだろうか?
 日本のピラフの定番「エビピラフ」
日本のピラフの定番「エビピラフ」
じつは、以前に<vol.26>「パエリアとワイン」で米料理の歴史を調べた際、ピラフには数千年に及ぶ壮大な物語が隠されていることを知ったのだ。「ピラフ」(pilaf)とはフランス語だが、その語源はトルコ語の「ピラウ」(pilav)だ。トルコ発祥とも、ペルシャ(現・イラン)発祥とも伝えられ、数千年前から食べられていたと推測される。ピラフは、トルコから中央アジアに伝わり、ウイグル人やキルギス人の間で広く食べられるようになったという。
歴史にはっきりと登場するのは、紀元前4世紀のアレクサンドロス大王の東方大遠征においてである。大王が率いるマケドニアの軍勢が古代ペルシャの州都サマルカンド(現・ウズベキスタン)を占領した際、饗宴の席において“米を炒めて炊き上げた料理”が出されたという記録が残っている。この料理法をマケドニアへ持ち帰り、そこからヨーロッパへも広まっていったと考えられている。
米は、アジアはもちろん、中東やアフリカ、ヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリアなど、世界中で食べられている。ただし、「白飯」つまり“白いご飯”として食べているのは、日本と中国、朝鮮半島くらいで、世界の大多数は“味付け米”としてがほとんどなのだ。ピラフと同じ料理は、インド・パキスタンでは「プラオ」、イランでは「ポロウ」、ウズベキスタンでは「パラフ」、ロシアでは「プロフ」と呼ばれている。
中でも発祥の国であるトルコの“ピラウ”は、オスマン帝国時代に宮廷料理として発展し、コース料理のメインとして扱われていたという。種類も豊富で、豆やナッツ、野菜、ザクロ、レーズン、羊肉、鶏肉、牛肉、魚介類など、さまざまな具材を使った多彩なピラウがあったらしい。トルコ料理は、フランス料理、中華料理と並び、世界三大料理の一つに数えられるが、ピラウはその豊かな食文化を構成する重要な要素だったのだ。
さらに、イスラム勢力の拡大はイベリア半島にも及ぶ。800年近くに渡るイスラム支配は、この地に米作りを伝えると同時に、ピラフも伝えたのだ。1492年のグラナダ陥落により、スペイン王国はレコンキスタ(失地回復)を成し遂げる。スペイン料理の代表といえば「パエリア」だが、これはもともと“金属製の鍋”という意味だ。この鍋で魚介や肉などを米と一緒に炒め、塩とサフランを加えたスープで炊き上げる。焦げが付くまで加熱するのがパエリアの特徴だが、もともとはピラフの流れを汲むものなのだ。
日本でも洋食の広がりとともに、ピラフがレストランのメニューに登場するが、普及にもっとも貢献したのは、<vol.37>「パスタとワイン」のケースと同様、喫茶店の軽食としてであろう。ただし、喫茶店メニューとしてのピラフは、炊いてある白飯をピラフ風の味付けで炒めたものがほとんどで、厳密にいうとピラフではない。チャーハン(炒飯)と同じ“焼き飯”の調理法に属するもので、“ピラフ風焼き飯”といっていい。
米や具材をあらかじめ炒め、出汁や香辛料を加え炊き上げるピラフは、手早く炒めるチャーハンや焼き飯に比べ、はるかに手間と時間がかかる。そのため、近年は業務用冷凍食品を使用している店が多くなっているが、本格的なピラフの調理法に則ったものを出すという意味では、冷凍のほうがむしろ正解なのである。
じつは、巻頭写真のピラフも味の素の冷凍物である。さすがに人気No.1商品だけあって、炒めたあとに炊き上げる本格調理法で作っており、ピラフ特有のふっくら感がよく出ている。また、ブイヨンの旨味が米一粒一粒の奥にまで浸み込んでいて、香り豊かでたいへん美味しい。
今回は、あっさり系のエビピラフだったので、ポルトガルの白ワイン「ヴィーニョ・ヴェルデ」で合わせてみた。鶏肉や牛肉、羊肉が入ったものや、トマト風味やカレー風味のものなら、トルコの代表的な赤ワイン「ヤクーツ」で合わせてみるのもおすすめだ。本格的なトルコ料理気分が味わえること、間違いなしである。

ヤクーツ(Yakut)
生産地:トルコ・東アナトリア地方カヴァクリデレ
生産者:カヴァクリデレ
品 種:オクズギョズ・ボアズケレ主体
価格帯:1900円(税抜)~