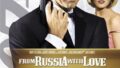2月中旬、雪まつりの観光客で賑わう狸小路を歩いていたら、やたらと繁盛している「タコとハイボール」という居酒屋があった。たこ焼きとハイボールをメインに出している店で、札幌以外に東北や関東にも出店しているらしい。ドリンクは他にも、ビールや各種サワー類はあるようだが、ワインはない。じつは、たこ焼きにはワインこそがおすすめなのだ。ということで、テイクアウトで持ち帰ってきたのだった。
 タコとハイボールの「九条ねぎマヨたこ焼き」
タコとハイボールの「九条ねぎマヨたこ焼き」
甘辛ソースで食べるなら、カベルネ・ソーヴィニヨンやテンプラニーリョ、プリミティーボなどフルボディ系の赤ワインが、まず基本となる。だし汁に浸して食べるならソーヴィニオン・ブランやアルバリーニョなどの白ワイン、または軽めのピノ・ノワールでも味が引き立つ。ハイボールをガブ飲みしながらでも悪くはないが、ワインでじっくり味わうたこ焼きも、また良いものなのだ。
タコは魚介の中でもっとも多くのタウリンを含んでおり、血圧やコレステロールを下げる効果があるとされる。また、プリプリの食感は噛むほど旨味があふれ、酸味や油を加えることで味わいがいっそう引き立つ。これにより、ワインは赤でも白でも全般的に合わせやすくなるといわれている。
それにしても日本人はタコが好きだ。たこ焼きだけではなく、刺身、茹ダコ、酢ダコ、タコ飯、タコザンギ(唐揚げ)、おでん、タコしゃぶなど、さまざまに食べられている。西洋人は一般的にタコは食べないといわれるが、ギリシャ、イタリア、スペインなど地中海沿岸の国とポルトガルは別だ。ギリシャでは炭火焼きにしたタコ焼きならぬ“焼きタコ”で、イタリアのナポリでは蒸し焼き、シチリアでは茹でてマリネにして、街の屋台などで売られているそうだ。
ポルトガルは、ヨーロッパでいちばん米を食べる国といわれ、日本のタコ飯に似た料理がある。オリーブオイルでタコやニンニク、米を炒めて炊き上げるもので、一見パエリア風だが焦げは付けないそうだ。スペインのガリシア地方は長大なリアス式海岸が続き、多数の漁師町が連なるエリアだ。茹でタコとジャガイモをオリーブオイルで和えた“タコのガリシア風”はタパスの定番として良く知られている。
漁師町の料理と言えば、BS朝日の「魚が食べたい!」は全国の漁港を巡り地元漁師さん自慢の魚料理を紹介する秀逸な番組で、毎週観るのを楽しみにしている。つい先週は道東の白糠漁港の特集で、当地名産のヤナギダコの刺身やザンギ、燻製、炊き込みご飯など、獲れたてのタコづくし料理が盛りだくさん。中でも、“タコマンマ”と呼ばれるタコの卵巣を使った自家製かまぼこは、見るからに旨そう!ぜひ、ワインと合わせてみたいものだと思ったのだった。
世界の各地には、さまざまなタコの食べ方があることはわかった。ただ、日本のたこ焼きに似たものはどこにも見当たらない。たこ焼きを特徴づけているのは、小麦粉を溶いて焼き上げた、あの独特の“ふわとろ”感だ。外側はパリッと焼き上げるが、中はトロリとした糊状のままで固形化はさせない。筆者の知る限り、このトロリ状態で食べる小麦粉料理は日本独自と言ってもいいようだ。
これは、いわゆる“粉もん(粉物)”文化の発展と大きく関わっている。小麦粉が中国から伝わったのは、奈良時代のこと。“小麦粉を溶いて焼く”という調理法は、安土桃山時代に千利休が「麩の焼き(ふのやき)」という茶菓子を作るために始めたともいわれている。この菓子は現在も京都の和菓子屋などで売られているが、ふんわり、もちもち感はあるが、トロリではない。
現在のたこ焼きは、1933年(昭和8年)大阪市西成区の会津屋が発祥とされる。当時の看板商品「ラヂオ焼き」を改良し、コンニャクやスジ肉の代わりに「明石焼き」で人気のタコを入れ、小麦粉を出汁で溶いて焼き上げたのが始まりだ。トロリ状態の決め手となったのは、出汁の量と小麦粉とのバランスである。その際に参考にしたのが、東京下町で食べられていた「もんじゃ焼き」らしいが、はっきりとしたことは不明だ。
たこ焼きの美味しさの本質は、タコ自体の旨味に加え、小麦粉と出汁のバランスが生み出す、独特の“ふわとろ”感にこそあったのだ。以前に<vol.34>「おでんとワイン」でも紹介した、イタリア南部プーリア州の「プリミティーボ」が出汁を効かせた料理に良く合い、またシチリアなどタコ産地の漁師料理にも合うのでおすすめだ。下記以外にも、さまざまな銘柄が出回っているので、たこ焼きのお供にぜひお試しを。

リッツァーノ プリミティーボ ディ マンドゥーリア マッキア
(Lizzano Primitivo Di Manduria Macchia)
生産地:イタリア・プーリア州
生産者:リッツァーノ
品 種:プリミティーボ
価格帯:1600円(税抜)~