「蕎麦屋で一杯」。これは、江戸時代から続く粋な食文化とされる。当時は、いまでいう“居酒屋”というものはなかった。正確に言うと、「居酒屋」という言葉自体はあった。酒屋で酒を買ってその場に居ながら飲むことを「居酒(いざけ)」と言い、そのような店が「居酒屋」と呼ばれていたらしい。つまり、現在の「角打ち」のようなものだ。それに対し、蕎麦屋では多彩なつまみや蕎麦を酒と一緒に楽しめるということで、多くの庶民の人気を集めていたのだ。
 山わさびせいろと炊き込みご飯のセット
山わさびせいろと炊き込みご飯のセット
蕎麦屋で一杯の“一杯”とは、日本酒を指すのが普通だ。じつは、蕎麦はワインとも相性がいい。最近ではワインを置く店も増えてきているので、札幌の老舗でもある「まるき」へ行ってみた。注文したのは、「山わさびせいろ」と炊き込みご飯のセット、そして「まるきルージュ」とある赤のグラスワイン。中身は「マスカット・ベーリーA」だ。この品種は、昭和初期に新潟県で米国産と欧州産のブドウを交配して生まれた日本固有の品種だ。以来、長期間に渡り一応は「和食に合うワイン」というふれこみで親しまれてきている。
飲んだ第一印象としては「ブドウの味がする」と感じた。そんなことブドウから造られているのだから、当たり前だろ!と言われるかも知れないが、海外産のワインは決してブドウそのものの味がダイレクトにはしない。ブドウ果汁を発酵させ醸造する過程で、チェリーやカシス、ラズベリーなどさまざまな果実味を感じさせる複雑な集合体へと変化するのだ。マスカット・ベーリーAは、日本人にまだワインが馴染みが薄かった時代、ワイン=葡萄酒をいかに普及させるかを考え、ブドウ味を強調するように仕上げたのかもしれない。
蕎麦に関しては、さすがは正統派二八蕎麦だけあって申し分ない。山わさびの微かな甘みのある辛さがやや濃いめの蕎麦つゆのアクセントとなり、蕎麦との絡み具合も絶妙であった。それだけに<vol.12>でも述べたが、出汁系醤油味の和食にぴったりの最強ワイン「ピノ・ノワール」に合わせたら最高なのになあと、内心思わざるを得ないのであった。
ところで、蕎麦を食べる国は日本だけではなく、世界中にある。主な生産国は、中国、ロシア、カナダなどで、ヨーロッパの国々で蕎麦粉はさまざまな料理に用いられている。よく知られているものとしては、フランスの「ガレット(=蕎麦粉のクレープ)」、イタリアの「ピッツォケリ(=蕎麦粉のパスタ)」、ロシアの「カーシャ(=蕎麦粥)」、ウクライナの「ブリヌイ(=蕎麦粉のパンケーキ)」などがある。当然、これらの国々ではワインと合わせて食べられることが多い。
先日、浦臼町出身の友人・Y田さんから夏野菜を大量にもらった。それを使って、妻がラタトゥイユを大量に作った。筆者は、この手の料理が大好きなのだ。当然のことながら、赤ワインに合う!最初はそのまま食べていたが、ふと思いついて、蕎麦にかけて食べてみた。これが、じつに良く合う!和風が一気にイタリアンに変化した。上述のピッツォケリを食べたことはないが、おそらくこんな感じではないかと想像することが出来た。
さらに驚いたのは、先に食べていた「鯛のカルパッチョ」のソースが皿に残っていたので、蕎麦に絡めて食べてみると、これがまた素晴らしく合う!つまり、オリーブオイルとバジルにレモンという“鉄板イタリアンソース”が蕎麦と相性抜群なのだ。筆者にとっては大発見であったが、クックパッドで調べたら、その手の食べ方は山ほど載っていた。なるほど、蕎麦は世界中で食べられているわけだ。和風・洋風を問わず、さまざまな味付けを幅広く受け入れるのだ。
今回、まるきへ行ったのは昼時だったので、注文した蕎麦は一品だけだった。次回は、ピノ・ノワールを置いてある店を探し、板わさ、蕎麦味噌、蕎麦寿司に始まり、創作蕎麦料理も交えた夜のメニューをぜひ堪能してみたいものだと、新たな野望が芽生えるのであった。
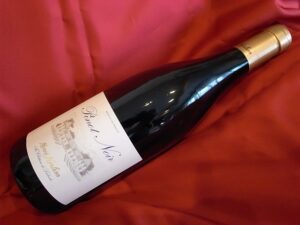
エルヴェ・ケルラン(Herve Kerlann Pinot Noir)
生産地:フランス・ブルゴーニュ地方
生産者:エルヴェ・ケルラン
品 種:ピノ・ノワール
価格帯:2000円(税抜)~


