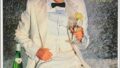中華料理店で、「あんかけ焼きそば」を注文することが多い。肉や野菜、海鮮がたっぷり入りとろみの付いたあんに、お好みでラー油数滴とお酢を少々垂らす。ビールや紹興酒を飲みながら食べれば、間違いのないうまさだ。もし、これにワインを合わせるのであれば、お勧めしたいのはロゼだ。微発泡性なら、なお良い。ということでポルトガルのロゼを巻末に挙げておいた。
 海鮮あんかけ焼きそば
海鮮あんかけ焼きそば
あんかけ焼きそばは、全国の中華料理店で置いていないところはまずない“中華の代名詞”とも言える定番メニューだが、じつは本場・中国生まれの料理ではない。焼きそば自体は中国語で「炒麺(チャウメン)」と呼ばれ、古くから存在している。問題は肉や野菜を炒め、水溶き片栗粉でとろみを付けた「餡(あん)」なのだ。
片栗粉は中国でも料理に頻繁に使われるが、素材にまぶしてコーティングし、うま味を逃さないために用いられるもので、“とろみ”を付けるためのものではない。「餡」とはもともと“詰め物”の意味で、餃子や焼売、春巻き、饅頭など点心の具材として、肉や野菜を混ぜたものが古来より中国では用いられてきた。では、いったい水溶き片栗粉でとろみを付けた餡は、どこでどのようにして生まれたものなのだろうか?
答えは、19世紀半ば米国の「チャイナタウン(中華街)」である。米国には大小50を超えるチャイナタウンが存在するが、1850年代にサンフランシスコで誕生したものが最初とされる。時はゴールドラッシュの真っ只中。カリフォルニアで金鉱が発見され、多数の人々が殺到した時代である。この頃に、現地のチャイナタウンで人気を呼んでいたのが「チャプスイ(雑砕)」という料理だ。
チャプスイとは、肉や野菜、ハムなどを炒め、スープを加えたあと、水溶き片栗粉でとろみを付けたものだ。「炒める」=【stir-frying】という調理法は欧米にはなかったもので、比較的少量の油で高温加熱することで、短時間に手早く料理することが出来る。これにとろみを付けることで全体に味が馴染み、極上のソースを絡めたような深い味わいとなる。そのまま八宝菜のように食べても良いし、餡として中華麺やマカロニ、白飯などにかけて食べても良い。本場・中国にはないけれど、アメリカ人の好みに合わせて生み出された“米国式中華料理”だったのだ。
さらに、チャプスイの人気を定着させたのは、1896年の李鴻章の訪米とされる。李鴻章は清国の軍人・政治家であり、米国において国賓級のもてなしを受けた最初の中国人として知られる。この饗宴の席でチャプスイが出されたという説がある。真相ははっきりしないが、これを契機に、チャプスイをかけた炒麺が「李鴻章麺」、白飯にかけたものが「李鴻章飯」という名で呼ばれるようになり、全米各地のチャイナタウンに広まっていったという。
日本へは1920年代、当時を代表するモダンな料理として銀座アスターへ伝わったとされる。これが庶民の家庭料理として広まるのは、戦後の食糧難の時代である。野菜の端切れやあり合わせの具材を炒め、とろみを付ければ立派な料理になるのであるから、たいへん重宝された。敗戦により満州から引き揚げて来た人たちが全国各地に「町中華」を開店するのも、この時代である。チャプスイを炒麺にかけたものを「あんかけ焼きそば」、白飯にかけたものを「中華丼」、カニ玉チャプスイをかけたものを「天津飯」として、広まったと伝えられている。
また、名古屋には“名古屋めし”と呼ばれる一風変わった料理がいくつか存在する。そのひとつが、「あんかけスパゲティ」で、喫茶店などで気軽に味わうことができる。発祥は1961年(昭和36年)に市内の料理店で出されたものとされるが、大本のルーツをたどれば、前述の米国チャイナタウンに行き着くと思われる。
とにかく、チャプスイは手早く簡単、スピーディなのだ。冷蔵庫の片隅の余り物一掃にも効果を発揮する。現在、チャプスイという名で料理を出している店は、まずない。家庭料理としても、多様なあんかけ料理へと姿を変え、発展的に絶滅したといえる。そのルーツをいま一度確かめる意味でも、さまざまなうま味が凝縮されたとろみを、微発砲性のロゼワインを添えてぜひ味わってみてほしい。

フェイティセイラ ロゼ・微発泡(Feiticeira Rose)
生産地:ポルトガル・ミーニョ地方
生産者:カサ・デ・ヴィラ・ヴェルデ
品 種:ヴィーニャオン、トウリガ・ナショナル他
価格帯:1000円(税抜)~